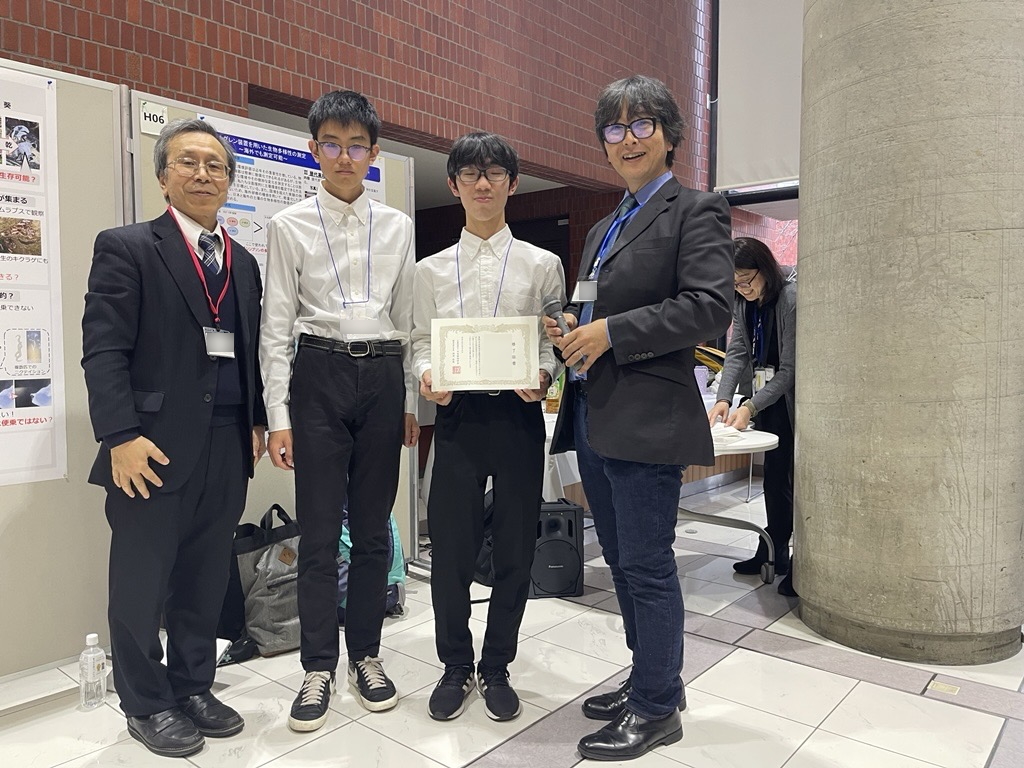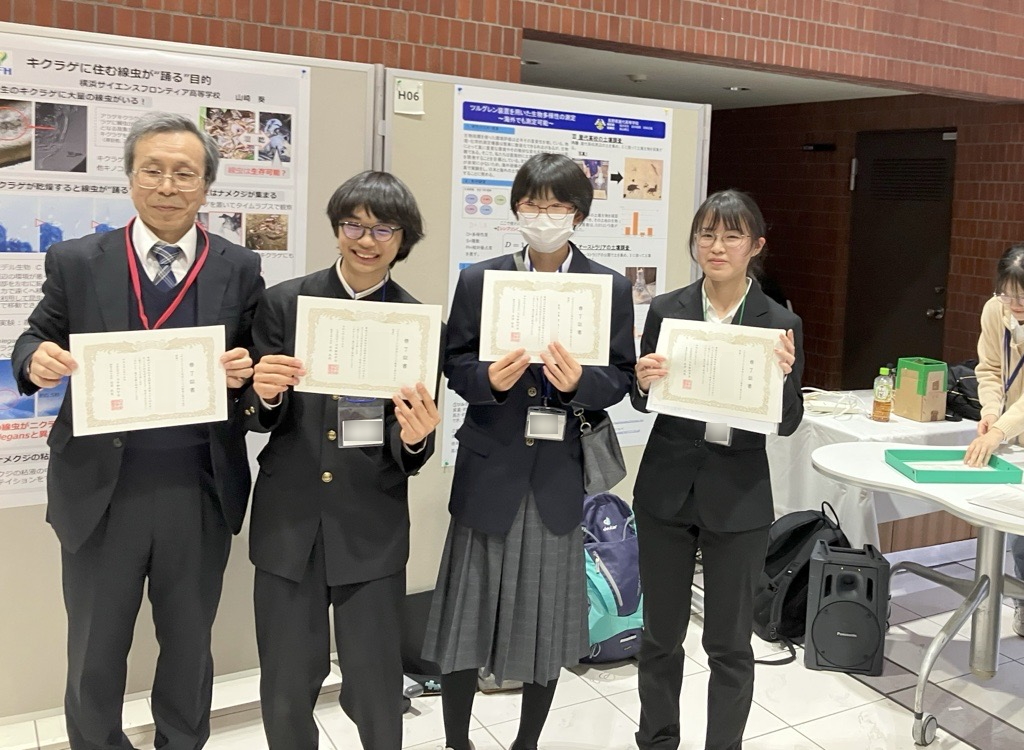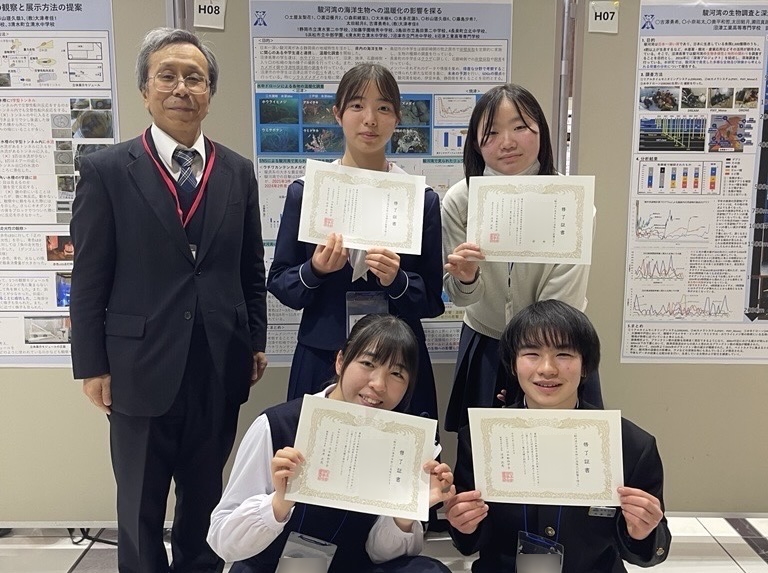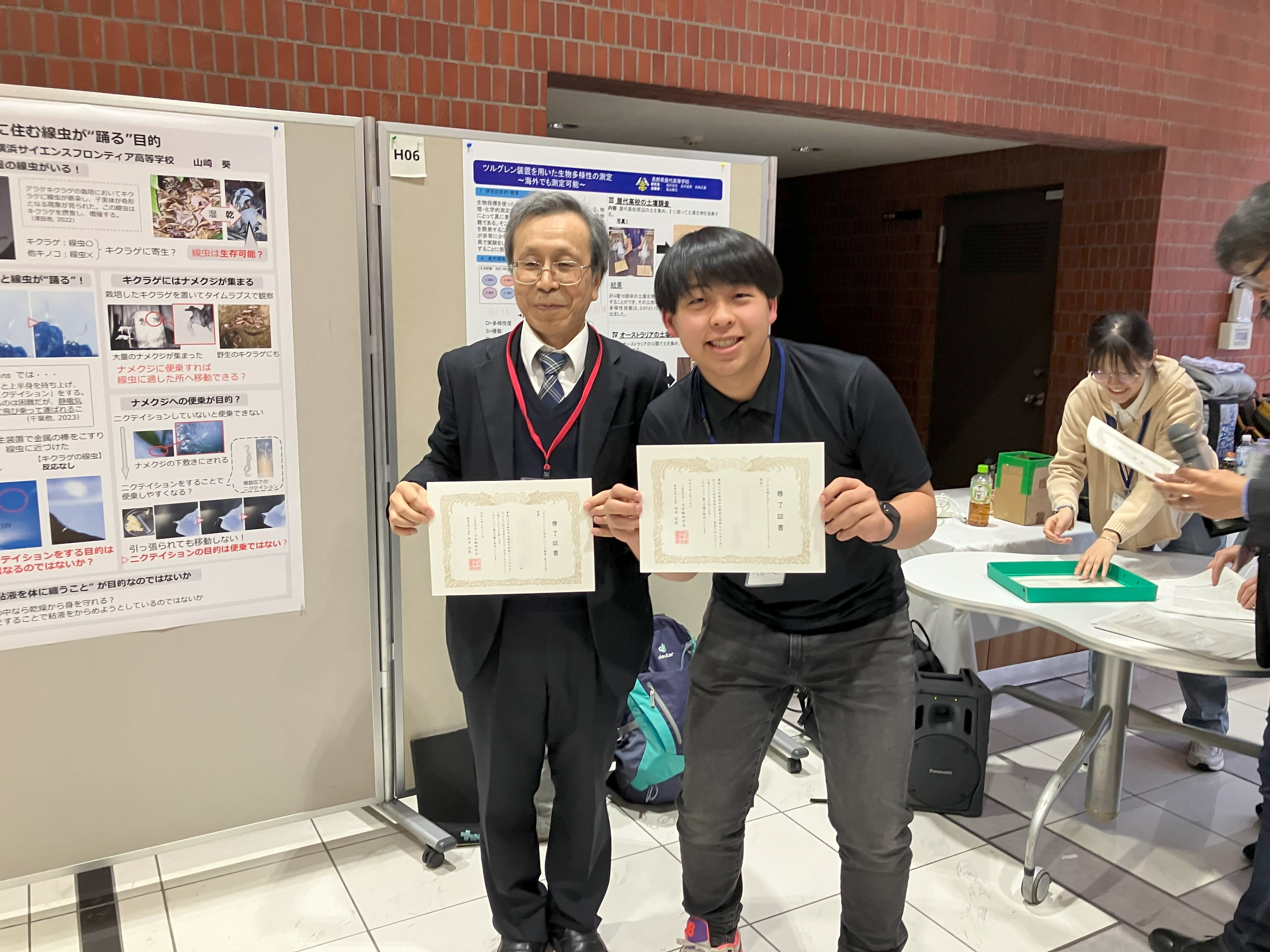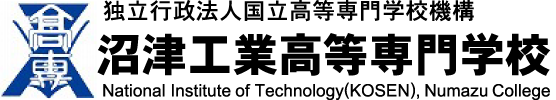電気電子工学科の大津教授は、課題研究「駿河湾とTRIZで深海の魅力を探求」の活動の一環として、県内外12校15名の小中高生と連携し、駿河湾の海洋生物への温暖化や黒潮の蛇行の影響、更に生物の環境進化についての探求学習を行いました。この活動の成果を令和7年3月15日に開催された日本動物学会関東支大会(茨城県つくば市産業技術総合研究所)で発表しました。
活動の概要
沼津高専の課題研究「駿河湾とTRIZで深海の魅力を探求」は、駿河湾を知財創造教育のキャンパスとして発想法TRIZ(トリーズ)を学び、地域課題の発見や解決に活かす選択授業です。本年度は1~5年生の50名が受講しました。更に、静岡県内外で深海生物や海洋生物に関心を持つ小学生3名、中学生11名、高校生1名も加わり、沼津港深海水族館、伊豆三津シーパラダイス、ヤマハマリーナ沼津、(有)松崎マリーナ、静岡放送(株)、笹川平和財団などの協力の下、深海の過酷な環境で生息する深海生物の持つ特徴からTRIZの40の発明原理探しを行うとともに、駿河湾の海洋生物の温暖化や黒潮の蛇行の影響、生物の環境進化などをテーマに探求学習を行いました。遠隔からの参加メンバーはTeams、LINE、Zoomなどで連絡し合いながら研究活動を行い、日本動物学会関東支部大会で、①駿河湾の深海調査、②オオグソクムシの行動観察、③駿河湾の温暖化の影響、④シーラカンスの環境進化、⑤アユの温暖化の影響、⑤バイオミメティクスワニ型ロボットに関する6件の研究の成果を発表しました。
発表の様子
日本動物学会関東支部大会には高専生3名を含む18名が参加し、各自のテーマで6件の発表を行いました。吉澤さん(沼津高専2年)、小奈さん(沼津高専1年)は「駿河湾の生物調査と深海における栄養源の分布」題し、深海カメラで撮影した深海2030mまでの映像データの解析からプランクトン数の温暖化の影響について報告しました。眞野さん(沼津高専3年)、藤島さん(沼津市立門池中1年)は「オオグソクムシの習性についての観察と展示方法の提案」と題し、駿河湾の深海生物であるオオグソクムシへのストレスを低減した展示方法を提案しました。土屋さん(静岡市立清水第二中2年)、本多さん(浜松市立中部学園1年)、渡辺さん(加藤学園暁秀中2年)、大本さん(長泉町立北中1年)は「駿河湾の海洋生物への温暖化の影響を探る」と題し、暖水系のカメガイ類、リュウグウノツカイ、ソラスズメダイ、タコクラゲなどの温暖化の影響について報告しました。森さん(島田市立島田第二中2年)、鷲見さん(岐阜県中津川市立坂本小5年)、中野さん(富士市立岩松小6年)、鳥居さん(島田市立島田第三小5年)は「シーラカンスの環境進化と温暖化への対応」と題し、シーラカンスやタコ/イカなどの溶存酸素量や海水温による環境進化についての調査結果を報告しました。杉山さん(清水町立清水中1年)、根本さん(清水町立南中2年)、小林さん(清水町立南中2年)、長倉さん(清水町立南中2年)、藤島さん(沼津市立門池中3年)は「アユの生態に及ぼす温暖化や海洋環境の影響」と題し、相模川、柿田川、天竜川のアユの生態について調べ、アユの温暖化の影響が地域環境によって異なることを報告しました。大塚さん(Harrow International School Appi Japan)は「ワニの生態を活かしたバイオミメティクスロボットの開発」と題し、ワニの高速歩行には骨盤や背骨が重要なことが分かりました。18名のメンバーは多くの専門家の前で、研究の成果を発表し、終了後、関東支部大会長より修了証書が授与されました。