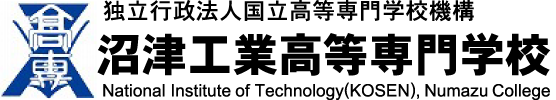三つのポリシー
学校案内
沼津高専の本科・専攻科では、以下に掲げる三つのポリシーに従って、教育活動を実践する。
このポリシーを基にして、教育の改革・改善に向けた検討を進める。
ディプロマ・ポリシーは、卒業・修了認定の方針である。
カリキュラム・ポリシーは、教育課程編成・実施の方針である。
アドミッション・ポリシーは、入学者の受入れの方針である。
本科
-
本校では、豊かな人間性を備え、社会の要請に応じて科学と技術の専門性を創造的に活用できる技術者を育成することを目的としている。そのため、学則で定める修業年限以上在籍し、全課程を修了して以下の能力を身につけ、167単位以上(一般科目75単位以上、専門科目82単位以上)を修得した学生の卒業を認定する。
- A 【倫理力】工学倫理に基づいて、社会問題に対する技術者の社会的責任を説明できる能力
- B 【基礎学力】数学、自然科学、情報科学・技術の知識を社会の要請に応えて活用する能力
- C 【専門力】工学分野の専門的知識を課題解決のために創造的に活用する能力
- D 【コミュニケーション力】多様な価値観の中で専門性を発揮し、コミュニケーションを取れる能力
- E 【実践力】実践的技術者として自身の役割を自覚し、計画的に課題解決学習や実験実習、および研究活動に取り組む能力
各学科の人材像は以下に示すとおりである。
機械工学科
機械や装置ならびにこれらに関連するシステムの開発・設計・製造の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者
電気電子工学科
電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者
電子制御工学科
電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者
制御情報工学科
コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者
物質工学科
化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者
-
ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を養成するため、以下の方針に従ってカリキュラムを編成する。国立高等専門学校機構モデルコアカリキュラム(MCC)に示された学習内容の実施と到達目標の達成が必修科目の修得だけで可能となるように配慮する。また、社会の多様なニーズに応えるために、各学科の特色や強みに関する科目(必修科目及び選択科目)を適切に配置する。
- A 技術と自然や社会との関わりや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について、技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明できる能力を身につけるため、人文・社会科学(社会)に関する科目を配置する。
- B 数学、自然科学及び情報科学・技術の知識を応用できる能力を身につけるため、数学及び自然科学(物理・化学)、情報基礎に関する科目に加え、各専門分野に関する専門基礎科目を配置する。
- C 工学分野の専門的知識を課題解決のために創造的に活用する能力を身につけるため、各専門分野に関する専門応用科目を配置する。
- D 多様な価値観の中で専門性を発揮し、コミュニケーションを取れる能力を身につけるため、人文・社会科学(国語・外国語)に関する科目、及び科学・技術系英語に関する科目を配置する。
- E 実践的技術者として組織・チームの中で自身の役割を自覚し、主体的かつ計画的に行動して課題解決学習や実験・実習・演習及び研究活動に取り組む能力を身につけるため、実技系科目を配置する。
なお、卒業研究はディプロマ・ポリシーに掲げたすべての能力を身につけるための科目として位置づけられている。
各学科の育成する人材像に基づき、以下のとおり編成方針を示す。機械工学科
機械系分野のMCC準拠科目を含めて、設計・製図、機械工作、機械・材料・熱流体の力学、制御・情報工学などの知識や技術を修得できる科目を配置する。
電気電子工学科
電気・電子系分野のMCC準拠科目を含めて、回路設計、電力変換、制御システム、情報通信、デバイスの知識や技術を修得できる科目を配置する。
電子制御工学科
電気・電子系分野と情報系分野の複合領域のMCC準拠科目を含めて、ロボット制御、データサイエンス、システム統合の知識や技術を修得できる科目を配置する。
制御情報工学科
情報系分野と電気・電子系分野の複合領域のMCC準拠科目を含めて、理工学基礎、プログラミング、コンピュータサイエンス、情報システムなど、情報工学/情報科学の普遍的な知識や技術を修得できる科目を配置する。
物質工学科
化学・生物系分野のMCC準拠科目を含めて、分析化学、無機化学、物理化学、有機化学、生物化学、化学工学の知識や技術を修得できる科目を配置する。
授業の実施と学修成果の評価の方針は以下に示すとおりである。
科目毎に到達目標、実施方法(授業計画を含む)、評価方法を定め、年度初めに公開する。学習成果の評価(成績評価)は100点法に基づくものとし、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
- 講義科目においては、主に試験(定期試験、小試験等)の結果や課題レポートなどの平常の取り組み状況に基づいて総合評価を行う。
- 実験・実習・演習(PBL科目含む)および卒業研究などの実技系科目・実践的科目においては、取り組み状況、成果報告または論文、発表などに基づいて総合評価を行う。
評語で表わす場合は、S(秀):100~90点、A(優):89~80点、B(良):79~70点、C(可):69~60点、D(不可):60点未満とする。
-
以下の意欲及び学力を有する者を、推薦選抜においては、調査書、推薦書、個人面接により、学力選抜においては、学力検査、調査書により、帰国生徒学力選抜においては、学力検査、調査書、エントリーシート、個人面接により、編入学選抜においては、学力検査、調査書、個人面接により確認し、受け入れる。
- 他人の意見を尊重し、社会の規範を守る者。
- 科学・技術に興味を持ち、入学後の学習に対応できる基礎学力を有する者。
- 豊かな教養と専門知識や技術を幅広く身につけたい者。
- 多様な価値観を受け入れ、自らの考えを表現できる者。
- 将来、科学者・技術者として地域・社会の発展に貢献する意欲の有る者。
学力の三要素(受け入れる学生に求める学習成果)との対応関係は以下に示すとおりである。
「知識・技能」 1、2
「思考力・判断力・表現力」 1、3、4
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」 1、3、4、5
専攻科
-
本校では、高等専門学校の教育における成果を踏まえ、工学に関する深い専門性を基に、創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備え、産業社会との学術的な協力を基礎に教育研究を行い、地域社会の産業と文化の進展に貢献できる技術者を育成することを目的としている。そのため、学則で定める修業年限以上在籍し、所定の単位修得条件の下で合計62単位以上を修得した学生の修了を認定する。
A 社会的責任の自覚と地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力
- (A-1)「異なる文化、価値観」や「自然との調和の必要性」を理解し、工学技術上の課題に対して地球・地域環境との調和を考慮し行動することができる能力。
- (A-2)「工学倫理」及び「社会問題に対して技術者の立場から適切に対応する方法」を理解し行動することができる能力。
B 数学、自然科学及び情報技術を応用し、活用する能力を備え、社会の要求に応える姿勢
- (B-1)数学、自然科学及び情報技術の知識を、環境エネルギー工学、新機能材料工学、医療福祉機器開発工学等の複合・融合領域に派生する社会的ニーズに応えるために活用することができる能力。
C 工学的な解析・分析力及びこれらを創造的に統合する能力
- (C-1)機械工学、電気電子工学、情報工学、応用化学、生物工学などの専門的技術を身につけ、これらの技術を複合的に活用して、環境エネルギー工学、新機能材料工学、医療福祉機器開発工学等の分野に創造的に応用することができる能力。
- (C-2)工学的に解析・分析した情報やデータをパソコン等により整理し、報告書にまとめることができる能力。
- (C-3)社会のニーズに応えるシステムを構築するために、エンジニアリングデザインを提案できる能力。
D コミュニケーション能力を備え、国際的に発信し、活躍できる能力
- (D-1)日本語で、自己の学習・研究活動の経過を報告し、質問に答え、議論することができる能力。
- (D-2)自己の研究成果の概要を英語で記述し、発表することができる能力。
E 産業の現場における実務に通じ、 与えられた制約の下で実務を遂行する能力並びに自主的及び継続的に自己能力の研鑽を進めることができる能力と姿勢
- (E-1)工学技術に関する具体的な課題にチームで取り組み、その中で担当する実務を適切に遂行することができる能力。
- (E-2)日常の業務や研究に関連した学会等が発行する刊行物を、定期的・継続的に目を通して実務に応用することができる能力。
各コースの人材像は以下に示すとおりである。
環境エネルギー工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野を融合複合した環境・エネルギー分野を中心に深く学修し、総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者
新機能材料工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野の基盤となる金属、セラミックス材料、高分子材料、生体材料などを深く学修し、総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者
医療福祉機器開発工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野を基盤とし、解剖生理学、医用生体工学など医工学分野を深く学修し、総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者
-
ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を養成するため、以下の方針に従ってカリキュラムを編成する。
A 社会的責任の自覚と地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力
- (A-1)「異なる文化、価値観」や「自然との調和の必要性」を理解し、工学技術上の課題に対して地球・地域環境との調和を考慮し行動することができる能力を身につけるため、一般科目(人文社会科学系)、コース専門科目(環境エネルギー工学系)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
- (A-2)「工学倫理」及び「社会問題に対して技術者の立場から適切に対応する方法」を理解し行動することができる能力を身につけるため、一般科目(工学倫理)、コース専門科目(環境エネルギー工学系、医療福祉機器開発工学系)、専門共通科目(知的財産)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
B 数学、自然科学及び情報技術を応用し、活用する能力を備え、社会の要求に応える能力
- (B-1)数学、自然科学及び情報技術の知識を、環境エネルギー工学、新機能材料工学、医療福祉機器開発工学等の複合・融合領域に派生する社会的ニーズに応えるために活用することができる能力を身につけるため、専門共通科目(数学、自然科学系)、コース専門科目(新機能材料工学系)、専門展開科目(選択)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
C 工学的な解析・分析力及びこれらを創造的に統合する能力
- (C-1)機械工学、電気電子工学、情報工学、応用化学、生物工学などの専門的技術を身につけ、これらの技術を複合的に活用して、環境エネルギー工学、新機能材料工学、医療福祉機器開発工学等の分野に創造的に応用することができる能力を身につけるため、コース専門科目(環境エネルギー工学系、新機能材料工学系、医療福祉機器開発工学系)、専門展開科目(選択科目)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
- (C-2)工学的に解析・分析した情報やデータをパソコン等により整理し、報告書にまとめることができる能力を身につけるため、専門展開科目(専攻科研究Ⅰ、Ⅱ)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
- (C-3)社会のニーズに応えるシステムを構築するために、エンジニアリングデザインを提案できる能力を身につけるため、専門展開科目(選択)、コース専門科目(環境エネルギー工学系、新機能材料工学系、医療福祉機器開発工学系)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
D コミュニケーション能力を備え、国際的に発信し、活躍できる能力
- (D-1)日本語で、自己の学習・研究活動の経過を報告し、質問に答え、議論することができる能力を身につけるため、専門展開科目(専攻科研究Ⅰ、Ⅱ)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
- (D-2)自己の研究成果の概要を英語で記述し、発表することができる能力を身につけるため、一般科目(語学系)、専門展開科目(専攻科研究Ⅱ)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
E 産業の現場における実務に通じ、与えられた制約の下で実務を遂行する能力並びに自主的及び継続的に自己能力の研鑽を進めることができる能力と姿勢
- (E-1)工学技術に関する具体的な課題にチームで取り組み、その中で担当する実務を適切に遂行することができる能力を身につけるため、専門展開科目(学外実習、実践工学演習、専攻科実験)でLevel4(分析レベル)までを身につける。
- (E-2)日常の業務や研究に関連した学会等が発行する刊行物を、定期的・継続的に目を通して実務に応用することができる能力を身につけるため、専門展開科目(専攻科研究Ⅰ、Ⅱ)でLevel4(分析レベル)」までを身につける。
各コースの育成する人材像に基づき、以下のとおり編成方針を示す。
環境エネルギー工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野を融合複合した、環境と新エネルギー、エネルギー変換工学及びエネルギー応用工学を中心に深く学修し、A-1,A-2,C-1,C-3に対応した能力を修得できる科目を配置する。それ以外の能力を修得できる科目を一般科目、専門共通科目、専門展開科目として配置する。
新機能材料工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野の基盤となる金属、セラミックス材料、高分子材料、生体材料の構造や物性、材料設計製作法について包括的に学修し、B-1,C-1,C-3に対応した能力を修得できる科目を配置する。それ以外の能力を修得できる科目を一般科目、専門共通科目、専門展開科目として配置する。
医療福祉機器開発工学コース
機械、電気電子、情報、応用物質などの工学分野並びに解剖生理学、医用生体工学など医工学分野を融合複合した、医用機器工学、福祉機器工学などを中心に深く学修し、A-2,C-1,C-3に対応した能力を修得できる科目を配置する。それ以外の能力を修得できる科目を一般科目、専門共通科目、専門展開科目として配置する。
教育課程表は以下の方針に従って編成する。
- 教育課程を一般科目、コース専門科目、専門共通科目、専門展開科目から編成する。
- 一般科目として必修科目(工学倫理、語学系)と選択科目(人文社会科学系) を配置し、必修 8 単位のほか、選択 2 単位以上を修得する。
- コース専門科目として選択科目(環境エネルギー工学系、新機能材料工学系、医療福祉機器開発工学系) を配置し、所属コースのコース専門科目を 10 単位以上修得する。
- 専門共通科目として必修科目(知的財産)と選択科目(数学、自然科学系)を配置し、必修2 単位のほか、選択 6 単位以上を修得する。
- 専門展開科目として必修科目(専攻科研究Ⅰ・Ⅱ、専攻科実験、学外実習、実践工学演習)と選択科目を配置し、必修 24 単位のほか、選択 10 単位以上を修得する。
- 設計・システム系科目群、情報・論理系科目群、材料・バイオ系科目群、力学系科目群、および社会・技術系科目群の 5 科目群に分類される科目を配置し、合計 6 科目以上、各群から 1 科目以上を修得する。
- ディプロマ・ポリシーに示される各能力に対応する科目を配置し、それぞれ 1 科目以上修得する。
授業の実施と学修成果の評価の方針は以下に示すとおりである。
科目毎に到達目標、実施方法(授業計画を含む)、評価方法を定め、年度初めに公開する。授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とする。評語と評価点の相互換算は、S(秀):90点以上、A(優):80点以上90点未満、B(良):70点以上80点未満、C(可):60点以上70点未満、D(不可):60点未満とする。
- 成績は、当該学期の試験の成績及び平素の成績並びに出席状況等を総合して決定するものとする。
- 実習の成績評価は、沼津工業高等専門学校専攻科学外実習規則によるものとする。
-
以下の意欲、学力及び経験を有する者を、推薦選抜においては、個人面接、自己申告書、成績証明書により、学力選抜においては、学力検査、個人面接、自己申告書、成績証明書、TOEICスコアにより確認し、受け入れる。
- 広い視野と深い専門性を身につけて、社会の発展、公衆の福祉に寄与する意欲を有する。
- 工学教育を受けるために必要な数学、自然科学及び英語の学力を有する。
- 基礎的な工学について、一定の指導と訓練を受け、実践した経験を有する。
学力の三要素(受け入れる学生に求める学習成果)との対応関係は以下に示すとおりである。
「知識・技能」1、2、3
「思考力・判断力・表現力」1、2
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」1、3
沼津工業高等専門学校のポリシー(三つの方針)裁定
沼津工業高等専門学校のポリシー(三つの方針)アセスメントプラン
本校は、ディプロマ・ポリシーで示された修得すべき能力を本校学生が獲得していくために、以下のアセスメント・チェックリストに基づいた本校の教育活動および学生の学修成果のアセスメント(評価)を実施します。3つのポリシー(ディプロマ・ポリシー(DP)、カリキュラム・ポリシー(CP)、アドミッション・ポリシー(AP))を全学レベル、学科・専攻レベル、科目レベルで総合的に点検・評価し、その結果を実施/担当部署にフィードバックすることによって継続的に教育改善を行っていきます。
この改善は、本校が毎年度作成し、意思決定会議である運営会議での承認を経たのちに、ウェブサイトで公開している「自己点検・評価報告書」により、その内容と継続的実施を確認することができます。さらに、外部からの意見を取り入れる機会である運営諮問会議でも報告し、教育改善の内容だけでなく、アセスメントが機能していることも検証します。
チェックリスト
-
項目/対象データ 内容 活用 担当部署 沼津工業高等専門学校の教育 教育目的、方針、学習・教育目標/AP/CP/DP 社会情勢に応じた見直し 自己点検・評価委員会/連絡調整委員会/教務委員会/入試室/専攻科運営委員会 年度計画 事業計画策定と進捗確認 各部署の実施内容の検討・見直し 各部署/自己点検・評価委員会 自己点検・評価報告書 成果とPDCA状況の確認 各部署の実施内容の確認・改善 各部署/自己点検・評価委員会 卒業生・修了生アンケート 本校教育の有効性
卒業後の状況カリキュラム改善
DPの改善連絡調整委員会/教務委員会/専攻科運営委員会 企業アンケート 本校教育の有効性
卒業後の状況DPとAPの見直し
カリキュラム連絡調整委員会/教務委員会/専攻科運営委員会 入学者アンケート 入学動機 APの見直し 入試室/入試国際交流係 入試分析 志願者学力、志願者の動向 APの見直し 入試室 実施項目 実施内容 結果の活用 担当者/部署 単位認定 単位取得状況 学生への履修指導
授業レベルまたは学生の到達度の確認教務委員会/専攻科運営委員会 進級・卒業状況 進級/卒業率 卒業/進級要件の見直し
カリキュラムの見直し教務委員会/専攻科運営委員会 進路調査 就職/進学先 DPの見直し キャリア支援室 外部試験/検定 TOEICおよび各種資格試験/検定での得点/認定状況 教育水準の妥当性の客観的評価 教務委員会 学生調査 学びの状況/高専生活の調査 学生生活満足度の把握と改善 教務委員会/専攻科運営委員会/学生委員会 MCC対応・カリキュラムマップ DP/CPおよび教育目的の達成が可能な状況の確認 カリキュラムおよび授業内容の見直し 教務委員会/専攻科運営委員会 実施項目 実施内容 結果の活用 担当者/部署 シラバス シラバスの点検 授業実施方法および内容の見直し 教務委員会/専攻科運営委員会 授業実施状況 授業アンケート 授業実施方法/内容/評価方法/カリキュラムの見直し 教務委員会/専攻科運営委員会 授業改善 授業改善報告書 授業実施方法/内容/評価方法の見直し 教務委員会 答案等評価試料 試験をはじめとする評価方法の確認/点検 成績評価方法および内容の見直し 教務委員会 MCC対応・カリキュラムマップ DP/CPおよび教育目的の達成が可能な状況の確認 カリキュラムおよび授業内容の見直し 教務委員会